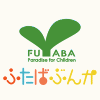これからの社会をよくするのは!

作家で心理学者の加藤諦三さんが、「これからの社会を良くするのは、経済人でも政治家でもない。幼稚園・保育園の先生だ」と書いていました。どういうことでしょう。
日本は、大借金国だけれど、まだまだ経済的には豊かな国です。しかし、自殺者が20年以上3万人を超えています。交通事故死者の5~6倍に達しています。昨年、ブータン国王夫妻が初めての外国訪問に、震災後の日本を選んで下さり、爽やかな風を残して行きました。ブータンの前国王が、「ブータンのGNP(国民総生産)は、どのくらいか?」と聞かれた時、「我国は、国民がみんな幸福に暮らしているかどうか、ということを重視している。」と言って、GNH(国民総幸福量)が話題になりました。金銭的、物質的な豊かさより、精神的・心の豊かさ、幸福を目指すということです。
ブータンでは、国民の96%以上が幸福だ、と感じていて、自殺者も殆どありません。日本では70%以上の若者が、今の生活に満足しているとのことですが、自殺者やうつ病の患者が増えています。芥川龍之介が、自殺した時「漠たる不安」に苦しんでいました。今は、なんとなく満足しているが、これからどうなってしまうのだろう、というウツウツとした将来に対する不安、恐怖があるのでしょう。
不景気が原因だという人がいます。しかし、好況の時でも、自殺やうつの患者は減少しませんでした。逆に、景気の良い時の方が増えている、というデータがあります。ちなみに、お隣の韓国は、近年世界の輸出大国として経済発展著しいが、人口比の自殺率は世界の中で群を抜いて高くなっています。
そろそろ社会の在り方、私達の生き方を見直す時期にきているのではないでしょうか。能力の一面だけを計る受験をはじめとする競争に、駆り立てられる生活を見直し、一人一人が自己実現し、自己充実して、社会に役立ち自分の人生を楽しむ生活に切り変える時になっているのではないでしょうか。
そこで、最初の問に返ると、人生の脚本は、幼少期にできてしまうと言われています。自殺の原因は、幼少年期の生活に基因することが多いという報告もあります。幼少期には一人一人の子どもの自主性・自発性を大切にして、幼少期には幼少期にふさわしい生活を保障して、自己充実を計ることです。人といると楽しい、生きていることは楽しい、周囲の人々に愛されているという体験を、幼児期の生活の中ですることが大切です。だから、これからの社会を良くするのは、幼稚園・保育園の先生の役割なのです。